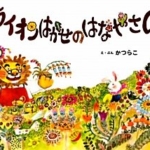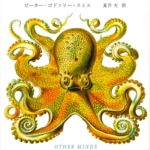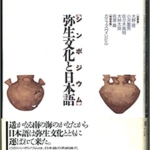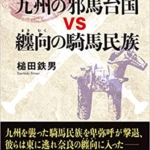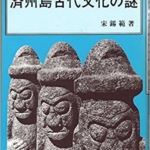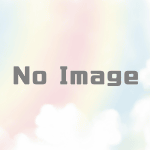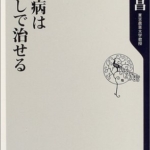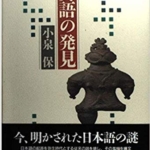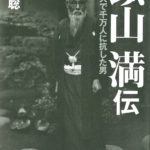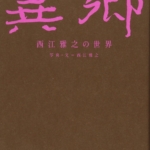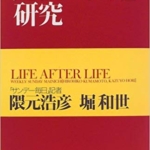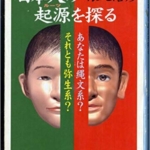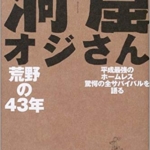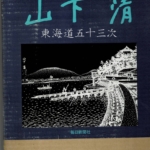「世界を操る支配者の正体」2014 馬淵睦夫(著) 講談社
すべての政治家と、政治活動に携わる人、そしてあらゆる現代人に、今もっとも読んで欲しい本。ロシアとウクライナの戦争や、LGBT・ジャニーズ問題に積極的な左翼の背景が見えてくる。 2014年に出版された本ですが、2023年の今、大きな意味を ...
「世界の台所博物館」1988 宮崎玲子(著)
火を使い、水を使って穀物や肉を調理し、食べる。気候や歴史が台所空間のあり方に大きく影響する
伝統的住まいの探訪に魅了された建築士が、1982年の建築士会の催しで、それまでに世界各地で集めた資料のまとめ方を検 ...
縄文生活の再現 (ちくま文庫) 文庫 – 1988/7/1
楠本 政助 (著)
出土品にならって釣り針をつくり、魚を釣る。モリで魚をつく。土器を焼いて使ってみる。竪穴式住居を作る。縄文時代の暮らしがよみがえる。縄文時代に使われていたという釣り針を見て、本当にこんな大きな針で魚が釣れたのだろうかと考えたことはないでしょう ...
「ライオンはかせのはなやさん」大型本 – かつらこ (著) 2010/2/11 1月( BL出版 )
種から育てた鉢植えのタンポポをうさぎくんからもらったライオンはかせ。いいことを思いつきますがとんでもない結果に。
小さい子ども向けの絵本ですが、遺伝子組み換えによる植物の作り替えに対して、「それはいいことではないよね」という理由がなんと ...
「PCRは、RNAウイルスの検査に使ってはならない」単行本(ソフトカバー)2020/12/3 大橋 眞 (著) ヒカルランド
今回のパンデミックはPCR検査が作り出している本を一通り読み終え、最初に戻って、扉の次に記された2行を読む
中国武漢から世界に広がったのは、ウイルスではなく、
PCRコロナ検査キットである ...
「タコの心身問題――頭足類から考える意識の起源」ピーター・ゴドフリー=スミス (著), 夏目 大 (翻訳)(みすず書房 2018年11月)
哲学者が生物の研究を通じて心を探究したこの本は、見逃していた不思議に目を向けさせ、生物である自分を再確認させてくれる
この本はある意味、脳の発達に的を絞った『新・人体の矛盾』であると言えます。哲学者としての視点から生物の進化を踏まえなが ...
『シンポジウム 弥生文化と日本語』単行本 1990年 大野晋、小沢重男、佐々木高明、大林太良、佐原 眞(出席)、カミュ・ズヴェレビル(寄稿) 角川書店
日本語は遥か南の海のかなたから弥生文化とともに運ばれてきたとする、日本語タミル語同系論を検証する
1989年に開催された、言語学者大野晋氏の主張する南インドのドラヴィダ系言語であるタミル語と日本語が同系であるとする主張を巡るシンポジウム ...
九州の邪馬台国vs纏向(まきむく)の騎馬民族 槌田 鉄男 (著) 352ページ 文芸社 (2019/10/1)
エンジニアとしての経験に基づいて事実を積み上げながら歴史を紐解く手法は、推理小悦を読んでいるような興奮をもたらす 私は日本の古代史に詳しくなく、この本に書かれている時代についてもあまり知識はありません。けれど、どうやら邪馬台国に卑弥呼がいた ...
「済州島古代文化の謎」1984/10/1 宋 錫範 (著) 206ページ 成甲書房
東アジアの複雑な歴史を象徴するような、大阪府ほどの大きさの島、済州島の古代文化を、島にルーツを持つ著者が探る
弥生時代の直前に当たる春秋時代(紀元前8―同5世紀)から前漢時代にかけての江蘇省の人骨と、渡来系弥生人(倭人)の人骨で、DNA ...
「マタギ―消えゆく山人の記録」1997/6/1 太田 雄治 (著) 慶友社 単行本
当初1979年発行された、30年にわたる調査・取材をまとめた狩猟民としての山人「マタギ」に関する現場主義的事典この本は体系立てて編集したり、解釈を加えた性質のものではなく、秋田魁新報社に勤めた著者が長年にわたって収集した資料を写真とともに収 ...
糖尿病は薬なしで治せる (角川oneテーマ21) (日本語) 新書 – 2004/9/10 渡辺 昌 (著)
糖尿病といっても自覚症状のない高血糖症の状態で、膵臓の機能がそれほど低下していないときに、食べ物と運動によって血糖値をコントロールすることで、一病息災を得る。薬の副作用についての説明もわかりやすい。
こうした本の多くは、読み進めていくと ...
蝦夷の古代史 (平凡社新書 (071)) (日本語) 新書 – 2001/1/1 工藤 雅樹 (著)
考古学者の視点から、古代の東北地方に暮らした「蝦夷(えみし)」と呼ばれた人びとの古墳時代から平安末期までの軌跡をたどり、縄文人の子孫がたどった複数の道を探る
あとがきによると、本書は、同著者による『古代蝦夷の考古学』『蝦夷と東北古代史』 ...
「縄文語の発見」1998/5 小泉 保 (著)279ページ 出版社: 青土社
弥生語が縄文語を駆逐したと決めてかかるのではなく、方言分布、アクセントの発生、特殊仮名遣いの成立、連濁現象、四つ仮名もの問題など言語学的に分析して、日本語の基底としての縄文語の復元を試みる 縄文人はどのような言葉を話していたのか。邪馬台国で ...
万葉集の言葉と心 (1975年) 中西 進 (編集) 228ページ 毎日新聞社
昭和49年に2日間にわたって行われた講演とシンポジウムを元に編集された、古代アジアの文化の中に置いて『万葉集』を解釈する取り組みの記録。 日本語はどこでどのようにしてできたのかを知るうえで役立つかもしれないと考えて読んでみました。
頭山満伝―ただ一人で千万人に抗した男 (日本語) 単行本 – 2015/8/6 井川聡 (著) 単行本: 624ページ 出版社: 潮書房光人新社
私たちは野口英世や渋沢栄一のことは教わっても、このアジアの真の独立を目指した人物のことは教わらない。 『謎の探検家菅野力夫』で頭山満という人物を知りました。
この本は、安政二年(1855)生まれの頭山満が、明治12年(1879) ...
異郷 西江雅之の世界 単行本 – 2012/4/28 西江 雅之 (著, 写真) 208ページ 出版社: 美術出版社
ハダシの言語学者兼文化人類学者が1967年から2010年までに撮影した写真と、発表したエッセイの再録作品。東アフリカ、カリブ諸島、ニューギニアなど、黒い肌が目立つ。
『「ことば」の課外授業―“ハダシの学者”の言語学1週間』の西江雅之さん ...
「死後の世界」研究 単行本 – 1997/8/1 隈元 浩彦 (著), 堀 和世 (著) 単行本: 239ページ 毎日新聞社
生まれ変わりや、臨死体験をまじめに科学する研究者、日本の生まれ変わり事例の現地調査、死後の世界を信じる作家たち、否定的な人びとなどを通じて、死後の世界について考える
「魂」があり、死後も存在し続けて、生まれ変わったり、死者を迎えに来たり ...
日本人の起源(ルーツ)を探る―あなたは縄文系?それとも弥生系? (新潮OH!文庫) 文庫 – 2001/2 隈元 浩彦 (著)
日本人は、元々住んでいた均質性の高かった縄文人に、殷のできた頃に中国大陸から朝鮮半島南部や日本列島に逃れた倭人が加わり、さらに渡来人が混じりあってできたのだろうか?本書は、骨格、遺伝子、墓の形状、使われていた道具、ATLウイルスの保有率、血 ...
洞窟オジさん―荒野の43年 平成最強のホームレス驚愕の全サバイバルを語る 単行本 – 2004/4/1 加村 一馬 (著) 小学館
昭和21年生まれの男性が、13歳から57歳まで、住所不定無職で過ごした43年間の記録。彼は「洞窟オジさん」というよりも「洞窟少年」であり、都会に住めないホームレスであった。当事者であり、著者として記載されている加村さんは、昭和21年8月生ま ...
東海道五十三次 (1971年) 山下 清 (著) 毎日新聞社 大型本 146ページ
東海道新幹線が開通したばかりの時期に、フェルトペンで書かれたこの遺作は、むしろ各作品に添えられた文章が響く。長岡の花火の貼り絵や、芦屋雁之助による裸の大将で有名な山下清。彼の遺作となったのが、この東海道五十三次をフェルトペンで描いた作品であ ...