「アフリカの歴史 侵略と抵抗の軌跡」岡倉登志(明石書店 2001年1月)
アフリカの歴史を見ると日本の歴史が見えてくる
この本は、アフリカの長い歴史を知りたいと借りた本でしたが、奴隷貿易が始まった頃以降についてのみ扱われていたため、5分の1程読んで終えてしまいました。そこまでの部分でも日本の現在置かれている状況を思い知らされる記述が連続していました。
アフリカで奴隷貿易が始まった頃、日本でもキリシタン大名たちが日本人を奴隷として送り出していました。見返りに火薬を手に入れていました。アフリカで宣教師を退去させた頃、日本でも禁教令が出されました。加えて、幕府は火器の改良を禁止し、刀の時代に戻りました。
日本の今
奴隷制度を廃止しようとしたとき、西洋の多くの人々は、奴隷制度が割りに合わなったという理由からではなく、善意から奴隷制度に反対したことでしょう。フランスの人々は、アルジェリアの人々に文明の恩恵を与えることができると喜んだことでしょう。
プロパガンダはいつでも確実に効果を上げ、支配者たちの思い通りに物事が進んでいきます。
日本は、この本で述べられているような価値観を持った凶暴で執拗な相手(国際資本家/悪魔崇拝者)たちによって、TPPという新しい不平等条約を結ばされようとしています。
手間取っているとすれば、英仏の争いの地となったマダガスカルのように、まだ、相手が一枚岩でないことが背景になっているのでしょう。しかし、一方で、宗教を使い、一方で科学(自然科学と社会科学の両方、特に社会科学)を使いながら、彼らの目的が粘り強く実現されていっていることに、注目しなければならないと思います。
日本は今、悪魔崇拝者たちが奴隷制・植民地支配・民主主義(民主的とみせかけた支配)に続く新しい支配方法を模索している中で、このたくらみをどう見抜き、どう対処していくのかという課題を突きつけられているのでしょう。
追記:
『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』では、この頃の日本の状況が扱われており、当時の日本の政治家たちも、アフリカの政治家たちと同じに粘り強く、明晰であったことがわかります。
内容の紹介
奴隷貿易が開始されたころ、アフリカにはコンゴ王国、ベニン王国、モノモタパ王国、マタンバ王国(別名ンドコンゴ王国)、ソンガイ王国などの諸王国が存在した。これらの王国は、経済的・社会的特権を有する比較的強力な「王権」の支配下にあり、ある面ではヨーロッパの封建制と類似した制度を持っていた。また、地域差はあったものの、交易関係もある程度進んでいた。
これらの王国の為政者のなかでいち早く奴隷貿易がもたらす害毒に気づいたのは、コンゴ王国のジンガ=ムベンバ王であった。アフォンソというクリスチャンネームで知られているこの王が、ポルトガル王ジョアン三世に奴隷貿易にたいする抗議状を送ったのは、奴隷貿易が開始されてからまだ日の浅い一五二六年のことである。
損害がいかに大なるか計りしれません。と申しますのは、前記の商人らは日ごと、国の息子ら、わが貴族、わが臣、親族の息子たちを捕らえております。この盗人や心のよこしまな連中はわが王国の物品を密かに自分のものにしようとしてその人々をもさらい、彼らを売り払います。恐れ多くも、その腐敗と堕落ぶりがことのほかひどいために、わが国土にはすべて人かげを見ないほどでございます。……かくの如きを避けるためには貴王国から牧師、少数の学校教師ならびに聖礼用のぶどう酒と小麦粉以外の商品は望みません。しかるゆえに、願わくば陛下より代理人に、当地へは商人も前記以外の物資も送らないよう命令されんことを。と申しますのも、わが(コンゴ)王国には、いやしくも奴隷の取引あるいはそのはけ口もあるべからずというのが、われらの意志でございます。
しかし、ポルトガル側はアフォンソ王の要望を無視し続けた。また、沿岸地方の族長たちは奴隷貿易で甘い汁を吸っていたので、奴隷貿易は繁栄する一方であった。こうして彼の抱いていた不安は現実のものとなったのである。アフォンソがこの抗議状を書いてからちょうど三〇〇年後、ブラジルにおける奴隷貿易の禁止などによってポルトガル人がコンゴ王国から手を引いたときには、コンゴ王国はおびただしい数の人口を失い、かつて繁栄していた都市は静寂な村に変質してしまっていたのである。 -21-22ページ
奴隷貿易廃止運動に参加した人々のなかには、人道主義的立場から参加した善意の人々も多かった。しかし、産業革命を経た当時のイギリスにあっては、従来の商業資本に代わって産業資本が発展を遂げつつあり、彼ら産業資本家たちは前近代的な搾取形態である奴隷貿易よりも、アフリカを市場として開拓したほうが利潤が多いと考えるようになっていた。奴隷貿易は、資本主義がよりいっそうの発展を遂げるうえで今や桎梏と化していた。 -30-31ページ
探検家の重要な役割の一つとしては、「ルート探し」のほかに前節で述べたアフリカ人首長たちとの「不平等条約」の締結があった。この条約に基づいて、ヨーロッパ人は広大な地域を支配し、不当な条件でアフリカから原料を買い上げた(実質上は奪い取った)。 -33ページ
一八〇七年にイギリス議会は奴隷貿易の廃止を決定しているが、この決定は、イギリスとアフリカとの関係の一つの転換を象徴していた。すなわち、アフリカはイギリスにとって奴隷供給地としてではなく、市場としての価値を持つ対象になった。イギリスの軍艦が、奴隷の密貿易を監視するという口実の下に、大西洋沿岸に配置され、その武力を背景に、イギリスは市場の確立・拡張のために内政干渉を強めていった。それは植民地制服のための直接的な準備の開始を意味した。その活動は、主にアフリカ内部の対立をあおることによって、支配のための基盤をつくり出すことに向けられていた。イギリスは、その目的を果たすために軍事的手段と外交的手段を用いた。 -34ページ
北東アフリカのエチオピア(別名アビシニア)にたいしてもイギリスは内政干渉を行っている。スエズ運河の完成が近づくにつれて、紅海沿岸の後背地であるエチオピアの戦略的重要性が増加したためである。当時、エチオピアでは、北西部の小州の高官(ラスと呼ばれる)カサが、エチオピア統一の事業を遂行していた。彼は並はずれた冷静さ、丁重さ、戦略家としての才を持ち、自国の経済力、軍事力の弱体化は、切迫している外国の侵入の危機に対処できないことを洞察していた。彼は、一八五五年、ネグ(皇帝)に任ぜられ、セオドール(テオドロス)二世を名乗る。セオドール二世は、それ以降も南進を続け、国内統一をほぼ完了してから国内改革に着手するが、このとき、エチオピアの内乱状況をつくり出して侵略の機会をねらっていたイギリスとの衝突を余儀なくされた。内外の戦争が長期化するにつれ、戦争の重荷を負わされた農民たちは封建的諸侯に扇動されて一揆を起こし、皇帝は孤立した。
結局、かつては五万人を数えたセオドール二世の軍隊も、一八六八年には六〇〇〇人に減少してしまった。好機到来とみたイギリスは、セオドール側の二倍の軍隊を投入する。このときの戦いがマグダラの決戦であり、セオドール軍は六〇〇〇の兵のうち二三〇〇を失って敗退する。イギリス軍の司令官は完全降伏を要求したが、セオドール二世は、マグダラ要塞に立てこもって最後まで戦い、一六人の部下と一緒に英雄的な戦死を遂げた。セオドール二世の戦死は、イギリス人にエチオピア人の祖国愛の強さを知らせ、彼の死は決して無駄とはならなかった。その後、エチオピアは、イタリアのファシストに占領されたほんの一時期を除けば、帝国主義者に直接制服されることのなかったアフリカ大陸の例外的な国になるのである。 -36-37ページ
最後に、一九三〇年のアルジェリア征服百周年祭に製作されたビラに記されている文章を紹介しておきたい。そこには、”文明の使命”の美名に隠れた侵略国の大衆プロパガンダ、言い換えれば”帝国意識”形成の本音が凝縮されている。
アルジェリアは、一八三〇年以前には(オスマン)トルコ帝国内の一州でしたが、それは名ばかりで実際は完全に無政府状態の野蛮な国でした。百万住民が貧困に喘ぎ、強欲で野蛮な支配者たちの食い物にされていましたが、一八三〇年以来、フランスがその地に旗を打ち立てて住民を解放しました。繁栄する州、フランスの州となり、今では人口五〇〇万の土民が文明のもたらすあらゆる恩恵を享受しています。
ここでは、アブデル=カーディルら”土民”がフランスに抵抗した史実は、全く抹殺されている。 -41ページ
マダガスカルの抵抗
ヨーロッパ列強がアフリカにおける権力争いを利用して内政干渉を行ったように、アフリカ側がヨーロッパ列強間の矛盾を利用して抵抗することもあった。
軍事的拠点として、船舶の休息・補給地として、ヨーロッパ人に注目されていたマダガスカルへは、イギリスとフランスが競いあって軍事遠征を行った。フランスは、一八〇四年までにこの島のいくつかの要塞地点を領有していたが、ナポレオン戦争当時の一八一〇年に、イギリスがフランスにとって代わった。しかし、一八一四年のパリ平和条約では、またフランスの領有権が復活されたので、イギリスは、ちょうどそのころ部族的統合によって成立したホヴァ王国の支配者をイギリスの統制下に置くことを企て、マダガスカル支配の野望を遂げようとする。かくて、英仏のマダガスカル領有をめぐる争いはその後も継続し、マダガスカル側の抵抗は、当初この英仏両国の争いを利用する形で闘われたのである。
ホヴァ王国の創立者の息子ラダマ一世は、一八二五年に、いくつかの他部族を扇動しつつ彼に挑んできたフランス軍を撃退したのみならず、彼を攻撃してきたそれら諸部族をも勢力下に服従させた。このとき、ラダマ一世は、フランスの競争者であったイギリスの助力を得ていた。しかし、彼の後継者であるラナヴァルナ一世(女王)は、イギリスとフランス双方の侵略的意図を見抜き、両国を交互に退けている。まず、ホヴァを利用しようとしていたイギリスとの条約を破棄し、宣教師を追放した。彼らは、アフリカ制服の事業を文化面で手助けしていたからである。フランスのシャルル一〇世はこの時とばかりに、一八二九年、遠征軍を派遣したが、軍事技術の優越にもかかわらず完敗させられた。フランスは、この翌年に成立したルイ=フィリップ王政下においてもマダガスカルに軍隊を派遣し、イギリス軍と衝突している。
しかし、こうして英仏の競争を利用して抵抗するホヴァ王国にたいして、英仏も共同してマダガスカルへの圧力を加え始めた。一八三五年、ホヴァ王国の女王は、英仏両国の国王に、平和的通商関係だけを持ち、両国がマダガスカルの内政に干渉しないよう要請した。しかし、これにたいし英仏は共同して軍艦による威嚇的デモンストレーションを行い、さらに、一八四五年にも小規模ながら英仏連合艦隊がマダガスカルを訪れ、陸戦隊を上陸させている。しかし、こうした英仏共同作戦によってもマダガスカルを屈服させることはできなかった。そこで、フランスは策をめぐらし、王子ラコトをその影響下において即位させようと企てたが、この陰謀は女王に見抜かれてしまう。女王の死後、王子がラダマ二世の名で即位するが、彼のフランスへの従属的征服は民衆の憤りを喚起し、一八六三年五月、民族的反乱が起こり、王と側近は殺される。かくしてマダガスカルでは、この後一八九五年フランスに征服されるまで、 マダガスカル史上最大の政治家と呼ばれ、英仏の矛盾を自由自在に操り続けたライオリヴォニの執権下に、相対的に安定した時期が続くのである。 -43-45ページ








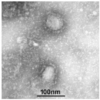


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません