「あと40年健康を保つ 自然食の効力」栗山毅一(著)(徳間書店 1968年11月)
生野菜と果実が人間本来の食べ物であることを指摘した昭和43年の本
タイトルの下に次の文言が掲載されています。
「生野菜と果実こそ人間本来の食べ物。煮物を避けて、鋭い頭脳・精力絶倫・長寿を保証する本」
『新・健康学「偏食」のすすめ―ヒトは果物を食べるように生まれついている』を読んで納得できていたので、この本も面白そうだと思い読んでみました。
本書はブルーバックスやカッパブックス同様の小型の本ですが、内容は充実しています。また、著者の栗山さんは97歳で亡くなるまで元気に活躍されたそうです。
人が果菜食動物であることだけでなく、現在も書店に並ぶ一冊の本の主題となっているような、食と健康に関するさまざまな内容が本書に詰め込まれていました。 それだけでなく、今まで聞いたことのないような内容も多く含まれており、真偽のほどはわからないまでも本書から受ける刺激は多そうです。
全体的に生野菜と果物、海産物の利用が推奨されており、春夏秋冬の季節ごとに5日分X3食分の献立表が掲載されています。
本書の概要を以下に示します。括弧内は該当するページ番号です。
・煮た物や焼いた物ばかり食べさせたサルは元気がなくなり性格も変わった。(25)
・ハウザー博士が有名にした葉緑素の大切さに、日本の片山淡博士は昭和8、9年頃には気づいていた。(44)
・抹茶を溶いて濾し、少量の塩を加えると応急的な目薬になる。(52)
・人間の歯と手と足は人間が山の麓で木の果実と地上の野菜を食べて生きる動物であることを示している。(58-59)
・葉緑素と血液はマグネシウムと鉄の違いだけで構造がそっくりである。(63)
・春は塩ぬき油ぬき、夏は体調の調整して血をきれいにし、秋から冬に吸収。(64)
・学問は朝早く、空腹でやる。(68)
・人間の生命を縮める原因の一つは動物性の油。(83)
(これは『ユダヤに伝わる健康長寿のすごい知恵』でユダヤ人が徹底的に油を抜くことと共通)
・胃は粉砕機であって頑丈だが、小腸は気化したものを吸収する精密機器。(87)
・エスキモーはビタミンCの欠乏を補うために、野イチゴを保存したり、鼠が貯えて種子を見つけて食べたりする。(88)
(聞いたことのない話ですが真偽はどうでしょう)
・天然水には栄養素がとけ込んでおり、外国では水だけで約1年間いきていた例があるという。(101)
・血液やリンパ液が濁った状態(アチドージス)は、ゴミ収集車がこなくなった町かどのような状態。(103)
・神経痛・リウマチ・痛風などは身体が弱アリカリ性を保っていればかからない。(107)
・夏の冷えを防止するにはブドウ糖とリン酸カルシウムがよいが、これらは西瓜と夏みかんを食べれば摂取できる。(114)
・人間本来の食事さえとっていたら、精力がなくなることもメンスが止まることもない。(118-119)
・頭のよい悪いは、主として、自律神経・ホルモン・生殖器をとりあつかい、蛋白質でできている間脳できまる。良質の蛋白質を補給することが肝心。(124)
・油をたくさん食べる外国では、アルコールも多く摂取して、体内からも油を燃焼させている。(126)
・身体に必要な塩分は微量であり、果物を食べることで補うことができる。(129)
・神経痛は塩分のとりすぎによることが多い。(134)
・糖尿病をなおすには、血液を弱アルカリ性にもどすことを主眼とすべきであり、カルシウムやビタミンを豊富にもっている果物や野菜をたくさんとる。(142)
・海水浴にはアメ湯(147)
・登山の酸素不足は生野菜を食べて小腸から補う。(146)
・母乳はもっともバランスのとれた栄養であり、乳児の成長とともに栄養価が変化する。(150)
・過剰なものを取り除くことが重要。「塩ぬき」「快便」「断食」。これも栄養だといえる。(151)
・人間は、腹の空いているときにはじめて抵抗力がでる。食後は休むが吉。(161-162)
・病人に肉や魚を食べさせるくらいなら、木の芽か青汁だけ飲ませていたほうがよっぽど回復が早い。(163)
・病人にもっとも適した食べ物は果物。(164)
・病気になったときは動物にならって断食するとよい。(165)
・人の身体は、胃で生きているのではなく、小腸で生きている。(197)
・小腸は吸収するところであり、ここが弱くなると死に近づく。(199)
・果物のスッパイのは果実酸といって、体内に入るとアルカリ性になる。酢を使うなら果汁からとった天然酢を使う。(208)
・バターやチーズは草食動物の油であって植物性の油である(類似植物性脂肪)。(211-212)
・種子には、吐きだされることを目的とし肥沃な土を必要としない大きな種と、食べられて糞と一緒に排出されることを目的とする小さい種がある。(231)
・大豆の生命力を利用するには生で唾液にまぶして食べるとよい。(232)
季節ごとに食物を変える視点や、身近にあるものを医薬品代わりに利用する知識にも感嘆させられます。
以下に目次を示します。
第1章 なぜ自然食が必要か 13
自然食とは 14
焼けこげたものがうまかった/便利なるがゆえの矛盾
脳で勝負する 16
四つの食事/精神は食物の反映/男も女も駈足で大きく
なる/ロボットになる人間/頭が悪いと早死する
動物には病気がない 24
野生のサルを観察する/文化のうらはら/毒を食べてい
る毎日/果菜動物である人間/多彩な食物に富む日本
四季の変化を忘れるな 31
自然のリズムに合った食事/無季の食事で頭がボケる/
不幸な加工人間
第2章 春の自然食 37
一年はアオから始まる 38
自然を失った生活/春はアオしかない/七草ガユの知恵
/毒消しと中和
ハウザー以前の先覚者 44
葉緑素を研究していた片瀬先生/緑と親孝行/肉食は性
質が荒くなる
お茶の効用 48
タンニンとカフェイン/医療用としての茶/抹茶の目薬
/生水を加えて飲む
木の芽で生きかえった話 54
芽を食べてもらう木/涙がでたので助かる/病鶏がつい
ばんだ草の芽/だから人間は野菜好き/アオは腐り止め
生命の三原色 60
花を食べて元気になる/ハゲは油のとりすぎ/大切な緑
の血
酸素欠乏は頭にくる 65
植物と海藻が酸素の提供者/吸って生まれて、吐いて死
ぬ/六時就寝・二時起床/小腸や皮膚からも吸う/ケン
カも酸素不足から/揺れない水は腐る
肉食の害 75
夜目が見えるのは肉食獣/牛肉は人肉にならない/消化
の魔術/中年太りになるわけ/肉嫌いに慢性病なし/油
っぽいのはゲス料理
栄養吸収の不思議 83
気体のままでは吸収されない/気化しやすいものを食べ
る/暴飲暴食の戒め
油をぬく季節 87
血液の酸化が命とり/太りだしたら死ぬ/デブの寒がり
/睡気から解放してくれる食事
<春の自然力>美しくなるために
第3章 夏の自然食 97
栄養豊富な地上の水 98
人体の七十五%は水分/水と動植物の栄養補給/ミネラ
ルがいっぱいの生水
生水の効果 102
いつも新しい水がいる/血液・リンパ液の濃度/神経痛
も体液のせい/水々しいのは若い証拠
夏は冷える季節 111
外が暑いと中が冷える/風呂とカロリー/温まる果物/
夫婦げんかに夏みかん/夏痩せと冷え症
スタミナとは温めること 117
死ぬまで精力はある/まちがっているスタミナ食/百ニ
十五歳まで生きられる/性ホルモンと間脳/中華料理と
西洋料理
塩気をぬこう 127
からすぎる日本料理/果菜のなかにある塩で十分/塩を薬
と思って使え/大切な塩ぬき/塩の害/冷えのもと
カロリーへの疑問 136
条件によって違う熱量/教科書にある説明/無意味なカ
ロリー分析表/病院での無理解
レクリエーションと食事 143
山と海でなにを食べるか/高度順化と生野菜/あめ湯の
効果/過剰を除くのも栄養学/水がおいしければ健康
<夏の自然食>夏負けしないために
第4章 秋の自然食 155
保温に役立つ澱粉 156
身体を作る主役/いも好きは長生き/含水炭素で太るの
ではない/猫も横を向いた一分間煮
少食礼賛 160
バカの大飯食い/満腹なら風邪をひく/病人の食事/ぶ
っそうな見舞品/鶴と亀は少食家/果物が嫌いだった
ら/二食か三食か/腹八分目に病なし
食事と記憶 171
空き腹で覚える/サラリーマンの弁当/昼休みの運動も
ほどほどに/記憶力と理解力/健康あったの判断力/脳
は栄養のエキス/鍛えた神経は鋭い/生きるも死ぬも酸
素次第/リズムで覚える/夢は脳波の再現/頭で消費す
る三割の酸素
<秋の自然食>頭をよくし、スタミナをつけるために
第5章 冬の自然食 191
栄養吸収のきめ手 192
次の飛躍にそなえて/人は油に向かって進む/哀れな胃
下垂患者/消化のトンネル・小腸
病気の予防 200
ビタミンの話/象はビタミンを食べていない/活気のも
とホルモン/中心になる間脳/ホルモンはお弥次郎兵衛/
荒れ性は油不足ではない/怒ったり疲れたりすると酸性
になる/蒸発する植物油/冷えの対策/冷えは万病のも
と医者を過信するな/高貴薬と高価薬
人生の楽しみ 220
同じ釜の飯/少なくなった”母を感じさせる人”/男の食
事、女の食事/夫婦和合は長寿のもと/離婚の理由/中
和のコツ/娯楽食の考え方/大きい種子と小さい種子/
眠りと休息の意味
<冬の自然食>冷えを防ぐために
装丁 斎藤明夫
本文イラスト 荒川寛
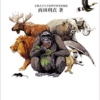
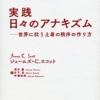

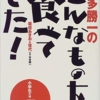
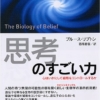
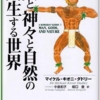
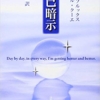
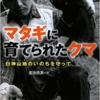
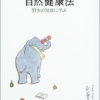
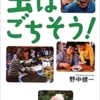
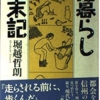
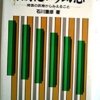
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません