「逝きし世の面影(平凡社ライブラリー)」渡辺 京二(平凡社 2005年9月)
明治の本当の姿を知るには、その前の時代を知ることが必要だ
→目次など
本の題名になっている「逝きし世」とは徳川期の日本、すなわち江戸時代のことです。
絶賛されながら一時絶版となり、出版社が変わって生き返った本書で、著者は、江戸末期から明治初期に来日した外国人たちの目を通じて記録された、当時の庶民の様子を拾い上げ、丹念に検討を加えています。
良く笑い、健康的であり、人混みでも秩序を保ち、親切心にあふれ、平等性を疑わず、裸体を罪悪視せず、子どもをしからず、動物たちと共に生き、歌や掛け声で労働を単なる作業から変質させ、生活を楽しむ人びと。江戸時代の日本は、外国人たちの目に、おとぎの国のようにもみえました。
これだけ読むと、自文化礼賛、「日本すごい」の本だと思われがちですが、著者の意図はそこにはありません。 近代の西洋やインド、中国が既に産業化の波によって庶民の貧困を経験する中、日本の貧困層は救われない存在ではなく、健康と幸福を保っていたことが指摘されているのです。
私たちは、理想郷の住人ではなく、生物として生まれ生物として死んでいく宿命を追った存在ですから、生はどうしてもつらく悲しいものになりがちです。 この生を、できるだけそのまま受け入れながら、しかも少しでも生きやすくしようとした徳川期日本の様子を知ることが、一方で理想を説き、不死を標榜しながら、他方で人の生をいよいよ辛いものにしている現代社会の実態を暴きだします。
かなり分厚く、難しい漢字も多く使われているため、普段から本を読む習慣がないと通読することは難しいかもしれません。私自身、引用のためにタイプしてみると読めない漢字の多さに驚きます。 それでも、目次とわずかな引用を読み直しただけで、この本を読まないことは一生の後悔になるといいたくなるだけの名著であると改めて感じるのです。
内容の紹介
第一章 ある文明の幻影
私はいま、日本近代を主人公とする長い物語の発端に立っている。 物語はまず、ひとつの文明の滅亡から始まる。
日本近代が古い日本の制度や文物のいわば蛮勇を振った清算の上に建設されたことは、あらためて注意するまでもない陳腐な常識であるだろう。 だがその清算がひとつのユニークな文明の滅亡を意味したことは、その様々な含意もあわせて十分に自覚されているとはいえない。 十分どころか、われわれはまだ、近代以前の文明はただ変貌しただけで、おなじ日本という文明が装いを替えて今日も続いていると信じているのではなかろうか。 つまりすべては、日本文化という持続する実体の変容の過程にすぎないと、おめでたくも錯覚して来たのではあるまいか。 – 10ページ
第二章 陽気な人びと
十九世紀中葉、日本の地を初めて踏んだ欧米人が最初に抱いたのは、他の点はどうあろうと、この国民はたしかに満足しており幸福であるという印象だった。 ときには辛辣に日本を批評したオールコックさえ、「日本人はいろいろな欠点をもっているとはいえ、幸福で気さくな、不満のない国民であるように思われる*1」と書いている。 ペリーは第二回遠征のさい下田に立ち寄り「人びとは幸福で満足そう*2」だと感じた。 ペリーの四年後に下田を訪れたオズボーンには、町を壊滅させた大津波のあとにもかかわらず、再建された下田の住民の「誰もがいかなる人びとがそうありうるよりも、幸せで煩いから解放されているように見えた*3」。 – 74ページ
*1、2、3 以下省略しますが、それぞれ出典が記されています。
第三章 簡素とゆたかさ
日本が地上の楽園などであるはずがなく、にもかかわらず人びとに幸福と満足の感情があらわれていたとすれば、その根拠はどこに求められるのだろうか。 当時の欧米人の著述のうちで私たちが最も驚かされるのは、民衆の生活のゆたかさについての証言である。 そのゆたかさとはまさに最も基本的な衣食住に関するゆたかさであって、幕藩体制下の民衆生活について、悲惨きわまりないイメージを長年叩きこまれて来た私たちは、両者間に存在するあまりの落差にしばし茫然たらざるをえない。 – 100ページ
第四章 親和と礼節
(前述のような楽園の姿にあこがれた後続の外国人たちを失望させた、疾患の多さや乞食の姿を描いた後で)
欧米人観察者が日本の古き文明に無批判ではなかったこと、それどころかしばしば嫌悪と反発を感じさえしたことは、以上のような事例を一瞥しても明らかである。 しかし、その批判者が同時に熱烈な賛美者でもありえたのはどういう理由によるのだろうか。 日本のさまざまなダークサイドを知悉しながらも、彼らは眼前の文明のかたちに奇妙に心魅かれ続けたのである。 彼らが書いていることを読むと、「この楽園には蛇がいないのではな」いと承知したうえで、なおかつ日本を「妖精の国」などと形容したくなる気持ちが手にとるように了解されてくる。
彼らはまず、先に見たように庶民の丁寧親切に印象づけられた。 一八五九(安政六)年に来日した宣教師ヘボン(James Curtis Hepburn 一八一五~一九一一)が、来日直後の印象を「一般民衆は丁寧で親切です」と述べ、同年来日してヘボンと同じ寺に住んだブラウン(Samuel Robbins Brown 一八一〇~八〇)もそっくりおなじ文句を繰り返しているように、これは一般の公論であった。 だが彼らはたんに丁寧親切であるのではなかった。 これもすでに見たように、彼らは無邪気で人なつこく、そして善良だった。好奇心にとみ、生き生きとしていた。 – 153-154ページ
第六章 労働と身体
スイスの遣日使節団長としてアンベールが日本に着いたのは一八六三(文久三)年四月、紆余曲折を経て修好通商条約をやっと結べたのが翌六四年二月、その十ヵ月間の見聞のなかで、彼もやはり、この国が「幾世紀もの間、質素であると同時に安易な生活の魅力を満喫してきた」ことに感銘を受けずにはいられなかった。 その感銘は彼を回想に誘った。 「私は幼年時代の終りごろに、若干の大商人だけが、莫大な富を持っているくせにさらに金儲けに夢中になっているのを除けば、概して人々は生活のできる範囲で働き、生活を楽しむためにのみ生きていたのを見ている。 労働それ自体が、もっとも純粋で激しい情熱をかき立てる楽しみとなっていた。 そこで、職人は自分のつくるものに情熱を傾けた。 彼らには、その仕事にどのくらいの日数を要したかは問題ではない。 彼らがその作品に商品価値を与えたときではなく――そのようなことはほとんど気にもとめていない――かなり満足できる程度に完成したときに、やっとその仕事から解放されるのである。 疲れがはなはだしくなると仕事場を出て、住家の周りか、どこか楽しい所へ友人と出かけて行って、勝手気儘に休息をとるのであった」。 – 236ページ
第七章 自由と身分
(日本人民衆が生活にすっかり満足しているようであり、それゆえに礼儀正しく親切であったことと、将軍による専制政治という現実を述べた上で)
大名行列の前に平服する庶民を見ればわかるように、世襲貴族と一般大衆のあいだには越えがたいへだたりがある。 「だが、ほかならぬこの理由のために、一般大衆のあいだには、われわれが想像する以上の真の自由があるのかも知れない」とオールコックは考える。 ヨーロッパの封建時代でも、人民が服従したのは、王や貴族の暴力が彼らまで到達するのがまれだったからだ。 嵐が高い木を痛めつける場合でも、ずっと下の灌木は無事なことが多い。 日本でもそういう事情は同一だろう。 「外見的な屈従は皮ひとえのものにすぎないのかも知れず、形式的外見的には一般民衆の自由があって民主的な制度をより多くもっている多くの国々以上に、日本の町や田舎の労働者は多くの自由をもち、個人的に不法な仕打ちをうけることがなく、この国の主権をにぎる人々によってことごとに干渉する立法を押しつけられることもすくないのかも知れない」。 – 263ページ
第八章 裸体と性
幕末来日した西洋人を仰天させ、ひいては日本人の道徳的資質さえ疑わせるにいたった習俗に、公然たる裸体と混浴の習慣があったことはひろく知られている。 日本は、西洋では特殊な場所でしか見られない女の裸が、街頭で日常的に目にしうるという意味でも「楽園」だったのである。 – 296ページ
第九章 女の位相
開国したこの国を訪れた異邦人の”発見”のひとつは、日本の女たちそれも未婚の娘たちの独特な魅力だった。 ムスメという日本語はたちまち、英語となりフランス語となった。 オイレンブルク使節団の一員として一八六〇年初めてこの国の土を踏み、六二年領事として再来日、七二年から七五年まで駐日ドイツ公使をつとめたブラント(Max von Brandt 一八三五~一九二〇)のいうように、「ムスメは日本の風景になくてはならぬもの」であり、「日本の風景の点景となり、生命と光彩を添え」るものだった。 – 342ページ
第十章 子どもの楽園
日本について「子どもの楽園」という表現を最初に用いたのはオールコックである。 彼は初めて長崎に上陸したとき、「いたるところで、半身または全身はだかの子供の群れが、つまらぬことでわいわい騒いでいるのに出くわ」してそう感じたのだが、この表現はこののち欧米人訪日者の愛用するところとなった。 – 388ページ
第十一章 風景とコスモス
欧米人たちに日本を楽園と感じさせた要件のひとつが、その恵まれた自然の美しさだったことはいうまでもない。 彼らは口を揃えてその美しさを讃美せずにおれなかった。 – 428ページ
第十二章 生類とコスモス
ホジソン夫人は長崎で領事館にあてられた寺に落ち着いたが、朝起きてベッドから足をおろすと、足もと数インチのところに蛇がいた。 彼女は悲鳴をあげ、召使を呼んで始末させたが、彼はその蛇をどうしても殺そうとはしなかった。 またある日、蛇は客間に侵入して、とぐろを巻いた。 先日の蛇とは別な奴だったが、そいつは「おれはもう一度やって来るぞ」といわんばかりに、彼女をにらみつけて立ち去った。 そして「約束どおり」二、三日後の夜、エヴァの枕もとを滑りすぎた。 ホジソン夫人はしばしばその蛇を庭で見かけたが、それを殺させることはできなかった。 蛇はお寺の主だったのだ。 – 482ページ
有毒なアオハブを無毒だと言って写真を撮影させた後で、ヘビを殺すのではなく枝ごと蛇を山に投げ込んだコノイ族を思い出しました。
第十三章 信仰と祭り
(中間部分を抜粋)民衆の意識においては、寺もまた神社とおなじく、彼らの現世の人生に幸福とよろこびを与えるものだった。 – 537ページ
第十四章 心の垣根
(中間部分を抜粋)
人びとを隔てる心の垣根は低かった。 彼らは陽気で人なつこくわだかまりがなかった。 モースが言っている。 「下層民が特に過度に期限がいいのは驚く程である。 一例として、人力車夫が、支払われた賃銀を足りぬと信じる理由をもって、若干の銭をさらに要求する時、彼はほがらかに微笑し哄笑する。 荒々しく拒絶した所で何等の変りはない、彼は依然として微笑しつつ、親切そうにニタリとして引き下がる」。 その事実にはすでに一八一〇年代に、ゴローヴニンが蝦夷の獄舎で気づいていた。 「日本人は至って快活な気風を持っている。 私は親しい日本人たちが暗い顔をしているのを見たことは一度もない。 彼らは面白い話がすきで、よく冗談をいう。 労働者は何かする時には必ず歌を歌う。 またたとえば艪をこぐとか、重い荷をあげるとか云ったような歌の調子に乗る仕事なら、皆が歌うのである」。 – 563ページ
追記(2019/3/8):
この本を読んでから5年ほど経つでしょうか。「命なんてしょせん不完全でどうにもならないものだ」ということを踏まえながら生きていたのが、このころの日本人で、そうした価値観を持っていたから、立派なことをいいながらカネだけに牛耳られるような世界にはならなかったのではないかと思えてきました。
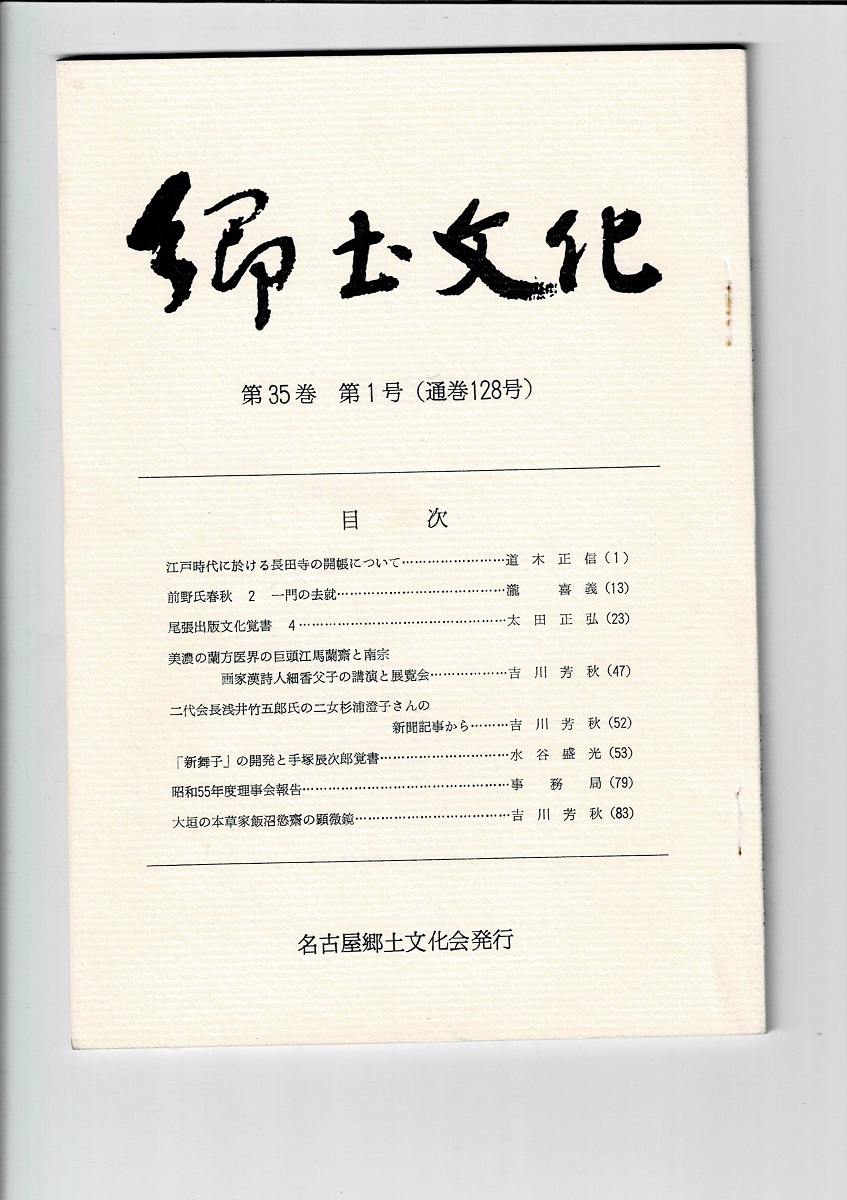










ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません