郷土文化 通巻69号 士朗特集(立川建築/朱樹叟士朗の研究/士朗150回忌始末記)
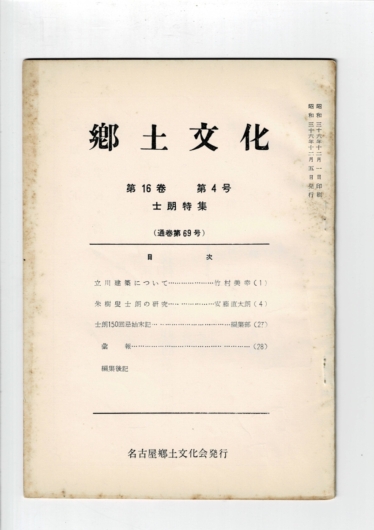
■目次
立川建築について…………………竹村美幸(1)
朱樹叟士朗の研究…………………安藤直太朗(4)
士朗150回忌始末記………………..編集部(27)
彙報……………………………(28)
編集後記
朱樹叟士朗の研究…………………安藤直太朗(4)
士朗150回忌始末記………………..編集部(27)
彙報……………………………(28)
編集後記
昭和36年発行 28ページ
■内容について
この号は、士朗特集と銘うったものの寄稿が少なく、結局「朱樹叟士朗の研究」のみが寄稿されたようです。編集部による「士朗150回忌始末記」を加えて体裁が整えられています。
「立川建築について」は立川和四郎を初代とする宮大工に関する記事です。内々神社の棟札の翻刻が収録されています。
「朱樹叟士朗の研究」は副題として「俳諧史上の位置」が掲げられています。冒頭部分を引用しておきます。
俳人井上士朗は名古星の人、その生涯を名古屋に住居し京都、江戸、伊勢に旅行はしたが、全く市井の雅人として終った。宗祗、芭蕉、蕪村、一茶の如く放浪漂泊の旅にその生涯を投げ出した人間ではなかった。しかも当時流行の町医としてその家業にいそしみ、何の屈託もなく生活に恵 まれた茶趣味の俳人として、全く大福長者の風格を具えていたといわれる。そして生涯を好ぎな俳諧の世界に遊んだ世にも稀なる幸福者であった。それほど当時声名のあった士朗も後世俳諧史家は彼を遊俳の一語に片づけて、世俗的な存在でしかあり得ないよぅな印象で迎えられているのは、文学作家として有難からぬ所遇であろう。しかし士朗にはたしかに遊俳としての面はあつたにしても俳諧点者に浮身をやつした宗匠気取りは微塵もなかった。暁台門の高足として当然暮雨巷二世を嗣ぐべき立場にありながら、恬としてこれを省みることなく、これを同門の臥央に譲つている。師暁台が蕉風の復古を唱道し、自ら蕉翁百回忌を取越、し主催し、京の蕪村と共に当時俳壇の立役者であり、且つニ条家より花の本の称号を得るために苦心したが、ヾ士朗に はそうした世俗的願望は無かった。もし暮雨巷二世をつぐとしたら、士朗の才幹と天分を以つてしたら、ゆうに海内に最も重きをなしたに違いない。彼はそうしたことに頓着はなかつた。いわゆる風月の長者として世間を達観していたのであろう。そこに彼の俳諧に、いやらしさというものがなく、温雅、平明で1種の気品のある微笑が漂っている。士朗の生活環境そのものがそうした大らかな人間をいつのまにか作りあげていたのである。彼は医を専業とする家を嗣いだ。
士朗については、井上 士朗 いのうえ しろうにわかりやすい説明があります。
尾張春日井郡守山(現 愛知県名古屋市守山)の生まれ。本名は井上正春。医名は専庵。初号を支朗、住まいに因み琵琶園・朱樹叟・枇杷園、隠居後は松翁と号した。少年時名古屋新町の町医者で叔父の井上安清の養子となり、3代目を継いだ。
10代後半ごろ俳諧を加藤暁台に師事。作品の初見は22歳の暁台編『蛙啼集』(宝暦13刊)。明和4年(1767)ごろより一門の間に重きをなし、天明の半ばには全国にその存在を知られるようになった。性格が温和で名利を追わず、藩医に推されたこともあったが辞退した。俳諧では、「尾張名古屋は士朗(城)で持つ」と俗謡にうたわれ、夏目成美、鈴木道彦と共に寛政三大家の一人として重んじられた。士朗の業績は、高雅にすぎた加藤暁台の句風を、大衆むきに平明化した点にあるが、反面次代の月並調の萌芽もみえる。
俳諧のほか、国学を本居宣長、絵画を勝野范古、平曲を荻野検校に学び、医者としても城下一の評判があった。
編著は『枇杷園句集』(1804)、『枇杷園句集後集』(1808)、『枇杷園随筆』(1810)、『枇杷園七部集』(1~5編)に収められる。<参考文献>市橋鐸「井上士朗」(明治書院『俳句講座』3巻)・岡本勝・雲英末雄編『近世文学研究事典』桜楓社)
「枇杷園士朗寫」の下に、白文の「朱樹」の落款印が押されている。











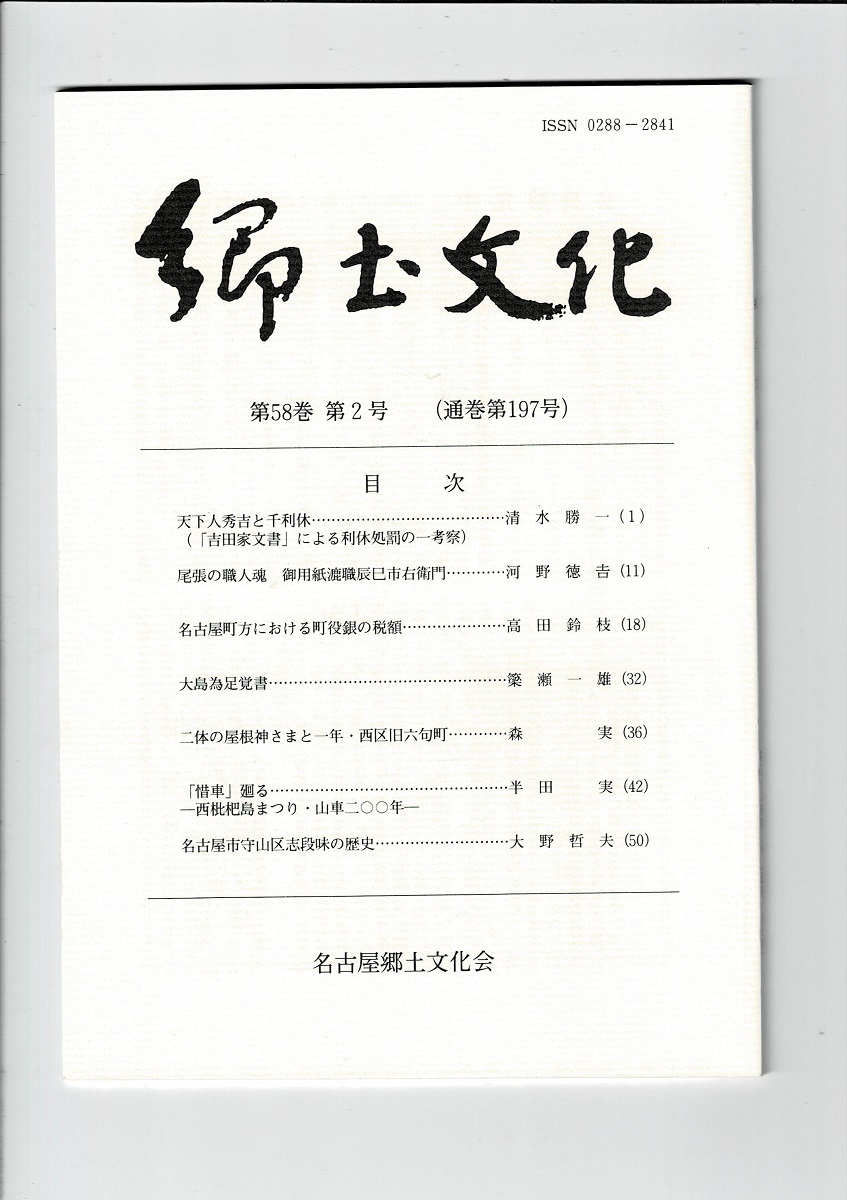
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません